「ブンブンジャーダサい」と検索してしまったあなた。実はその第一印象、あなただけではありません。SNSでは「語尾にブン?」「顔がタイヤって本気?」など、驚きとツッコミが飛び交い話題沸騰中です。けれど、その“ダサさ”がなぜかクセになってしまうという声も急増しています。本記事では、ブンブンジャーがダサいと感じられる理由をビジュアル・ネーミング・演出などから徹底分析。さらに、過去の戦隊シリーズとの比較や、実は隠された戦略的な仕掛け、そして人気の理由まで深掘りします。読めばきっと、「ダサいけど、ちょっと気になるかも」と思えるはずです。
- ブンブンジャーはなぜ「ダサい」と言われているのか?【総まとめ】
- 「ダサい」という声の出どころはどこ?
- 1-2. 視聴者の第一印象:X(旧Twitter)の反応分析
- 2. 【ビジュアル考察】ブンブンジャーの衣装やロボットがダサく見える理由
- 2-1. 丸みを帯びたフォルムと色使いのギャップ
- 2-2. 顔のマークは「タイヤ」?過剰なシンプルさへの疑問
- 2-3. ブンブン○○系ネーミングの統一感と限界
- 3. 「語尾にブン」はダサい?遊び心と違和感の境界線
- 3-1. キャラクターセリフと公式Xの文体に見る「ネタ感」
- 3-2. 他戦隊と比較して異質なのか?
- 4. キャストがイケメンすぎる問題:「見た目」と「設定」のギャップがダサさを強調?
- 4-1. 各キャラのプロフィール紹介と魅力
- 4-2. なぜイケメン起用でも「ダサい」と言われるのか?
- 5. 過去の戦隊シリーズと比べて本当にダサい?【比較レビュー】
- 5-1. 『カーレンジャー』『ゴーオンジャー』などとの比較
- 5-2. ダサさは「狙い」か「事故」か?
- 6. 「ダサい=話題性」の法則?バズ狙いの可能性を考察
- 6-1. SNSでの拡散性とマーケティング戦略
- 6-2. ダサさがクセになる理由とは
- 7. それでもハマる!ブンブンジャーの本当の魅力
- 7-1. 戦闘シーンの迫力とストーリー性
- 7-2. 子どもたちの人気はどうなっている?
ブンブンジャーはなぜ「ダサい」と言われているのか?【総まとめ】
ブンブンジャーに対して「ダサい」という声が目立つようになったのは、放送開始直後のSNSを中心とした口コミがきっかけです。確かに、名前のインパクトやビジュアルの特徴がユニークすぎて、初見で戸惑う方も多かったはずです。しかし、この“ダサさ”には理由があり、そこには狙いも感じられます。
まず名前ですが、「ブンブンジャー」という響きそのものが印象的で、子ども向けらしい明るさと親しみやすさがあります。とはいえ、大人からすると「ブンって何?」「ジャーってつければ何でもアリ?」といったツッコミを入れたくなるネーミングです。
衣装やロボットのデザインも、これまでの戦隊シリーズとは一線を画しています。丸みを帯びた車モチーフのロボや、タイヤを意識したフェイスデザインが多くの人にとっては“シンプルすぎる”と映ったのかもしれません。また、キャラクターが話す際に語尾に「ブン」がつくなど、作風全体に一種のコミカルさがあります。
このような要素が重なった結果、「ダサい」と感じる人が一定数出てきたと考えられます。ただし、その裏には意図的にキャッチーさを狙った演出や、子どもたちの記憶に残るデザインを目指した戦略が見え隠れしています。
以下に、視聴者がダサいと感じる主なポイントをまとめました。
| 指摘されるポイント | 内容の詳細 |
|---|---|
| ネーミングのユニークさ | 「ブンレッド」「ブンブルー」など、全員に“ブン”が付くネーミング。簡素でダサく感じられる |
| キャラの語尾 | 公式X(旧Twitter)での語尾が「ブン」。語調が幼く感じられると話題に |
| メカ・ロボのデザイン | 丸みを帯びたフォルムと“ブンブン○○”の名称が子ども向けすぎて幼稚に見える |
| フェイスマスクのマーク | 顔にあるシンプルな“タイヤ風”デザインがチープに映ると一部で不評 |
こうして見ると、「ダサい」と言われるのも無理はないように思えます。しかし、その“ダサさ”こそが、次世代の子どもたちには新鮮に映る可能性があるのも事実です。平成や令和初期の戦隊と比較すると、よりファニーで親しみやすさに特化した作風と言えるでしょう。
作品としての狙いがあるのは明白ですし、戦隊シリーズにおいて「ダサい=覚えやすい=人気」という構図は過去にも存在してきました。その流れを踏まえた上で、ブンブンジャーの“ダサさ”をどう受け止めるかが評価の分かれ目になっています。
「ダサい」という声の出どころはどこ?
実際に「ダサい」という声が出てきた場所は、主にSNSや掲示板、そしてYouTubeのコメント欄です。特に放送開始直後の2024年3月上旬には、X(旧Twitter)でのトレンド入りとともに、「なんだこのネーミング…」「語尾の“ブン”に笑った」などの反応が続出しました。
公式の投稿もまた、議論を呼んだきっかけの一つです。たとえば、2024年3月10日の公式X投稿では、「いかがだったブン?」という語り口が採用されており、これが多くのユーザーにとっては予想外だったようです。
また、玩具メーカー・バンダイのガシャポン公式アカウントでも、「ブンレッド」「ブンブルー」などのネーミングが紹介されており、これに対して「適当すぎる」「ネタなのか?」というコメントが多く寄せられていました。
さらに、「爆上戦隊ブンブンジャー」というシリーズタイトル自体にも違和感を抱いたという声が目立ちます。「爆上(ばくあげ)」という言葉がやや古く感じられたり、全体の語感が軽すぎる印象を与えるからです。
こうした反応を時系列で整理すると、以下のようになります。
● 2024年3月3日:テレビ朝日系列で初回放送
● 2024年3月4日:X上で「ブンブンジャー」がトレンド入り
● 2024年3月10日:公式Xで「いかがだったブン?」が話題に
● 同時期:バンダイのグッズ展開で名称が公開され、再び賛否両論が加熱
インターネット上の反応は、年齢層によって温度差が大きいという特徴もあります。20〜30代のかつて戦隊を見ていた層からは「最近の戦隊はふざけすぎ」という批判もあれば、小さい子どもと一緒に見ている親世代からは「子どもが喜んでるからアリ」という肯定的な声も見受けられます。
つまり、「ダサい」と感じるかどうかは、見る人の世代や価値観によって大きく変わるということです。そして、そのギャップこそがブンブンジャーという作品の注目される理由とも言えます。
1-2. 視聴者の第一印象:X(旧Twitter)の反応分析
放送が始まって間もない2024年3月上旬、ブンブンジャーに関する第一印象は、まさに「混乱と笑い」が入り混じったものでした。特にX(旧Twitter)では、初回放送当日のタイムラインが一斉に“ブンブン一色”となり、驚きやツッコミの声が続出しました。
まず、最も話題になったのが公式Xの文体です。3月10日に投稿された「いかがだったブン?」という一言が、それまでの戦隊シリーズにはなかった“語尾ブン”という独特なノリを印象づけました。
この投稿を受けてのリアクションには、以下のようなパターンが多く見られました。
主な反応パターン(Xの投稿内容に基づく分類)
| 反応タイプ | 投稿例 |
|---|---|
| 驚き・戸惑い系 | 「ブンて何!?」「語尾ブンはクセ強すぎw」 |
| ツッコミ・笑い系 | 「ブンブンジャー、名前も語尾も攻めすぎ」「これはネタ枠?」 |
| 懐かしさ系 | 「ゴーオンジャーを思い出す」「平成初期っぽいダサさが逆に好き」 |
| 好意的な評価 | 「子どもがめっちゃ笑ってた」「この振り切り方、嫌いじゃない」 |
とくに注目すべきは、否定的な意見が多数あった一方で、それを“ネタとして楽しむ空気”もすぐに形成されていた点です。これまでの戦隊ヒーローとは違い、最初から笑われる要素が盛り込まれているため、あえてツッコミ待ちの作風であると感じた視聴者も多かったようです。
一部の投稿では、初回放送中に「トレンド1位」を獲得したことも報告されており、話題性の高さは間違いありません。つまり、たとえ“ダサい”と思われても、それが拡散されて注目を浴びている時点で、戦隊としては成功のスタートを切ったとも言えます。
また、SNSでのリアクションは世代によって明確に分かれていました。
- 20〜30代:過去の戦隊シリーズとの比較で「違和感」や「方向転換」を指摘
- 10代以下:純粋にビジュアルや言葉のユニークさを楽しむ声が多い
- 子育て世代:子どもが喜んでいる様子をポジティブに受け止めている
こうした反応から、ブンブンジャーが「SNS時代のツカミ」を意識したコンテンツであることが読み取れます。第一印象の“ダサさ”が、逆に視聴者の心に残る武器になっているのは間違いありません。
2. 【ビジュアル考察】ブンブンジャーの衣装やロボットがダサく見える理由
視聴者の「ダサい」という評価を大きく左右しているのが、ビジュアル面です。戦隊ものにおいて、衣装やメカのデザインはシリーズの“顔”とも言える重要な要素ですが、ブンブンジャーでは従来の「カッコよさ」ではなく、あえて「ポップで親しみやすい」路線が採られています。
まず衣装のデザインですが、ベースカラーは戦隊伝統のレッド・ブルー・ピンク・ブラック・オレンジの5色で構成されています。しかし、それぞれのスーツは直線的なラインや鋭いモチーフではなく、どこか「おもちゃ感」が強く出ているのが特徴です。
ブンブンジャーの衣装デザインで特徴的な要素
- 胸元や肩に「タイヤ風」モチーフを大きく配置
- 丸みを帯びたフォルムで未来的というよりもレトロな印象
- シンボルマークが大きくて主張が強く、全体的にチープさを感じさせる
特にマスクのデザインについては、「顔がシンプルすぎる」「あれ、これって某お菓子のキャラクター?」などと比喩されることもあり、視聴者の間で賛否が分かれています。
次にメカ・ロボのビジュアルですが、これも“ブンブン”という名前にふさわしく、車をベースにしたフォルムで統一されています。具体的には、
- ブンブンスーパーカー
- ブンブントレーラー
- ブンブンオフロード
- ブンブンワゴン
といった名称で、それぞれがコミカルな丸みを帯びたデザインになっています。
ロボットビジュアルの特徴と評価
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フォルム | 丸みを帯びた車型で、近未来感よりも玩具感が強い |
| ネーミング | 全て「ブンブン○○」という統一感はあるが、子どもっぽさが強調されている |
| 組み合わせ | 合体時もゴツさよりは可愛さ重視で、威圧感は少なめ |
| 色のバランス | カラフルさはあるが、大人の目には派手すぎて安っぽく感じることも |
こうしたビジュアルは、たしかに「カッコよさ」を重視する大人層からは「ダサい」と感じられる可能性があります。しかし、子どもにとってはこの“わかりやすさ”と“親しみやすさ”がハマる要素になっているのも事実です。
近年の戦隊シリーズは「グッズ展開ありき」での設計が多く、玩具としての完成度や安全性も考慮されています。そのため、ブンブンジャーのデザインも「ダサい=覚えやすくて売れる」というマーケティングに基づいている可能性が高いです。
つまり、大人にとっての“ダサさ”は、子どもにとっての“カワイイ”や“楽しい”に直結しているという見方もできます。ビジュアルだけを見て評価を決めるのではなく、ターゲットの視点で再評価してみると、意外な魅力に気づけるかもしれません。
2-1. 丸みを帯びたフォルムと色使いのギャップ
ブンブンジャーのデザインで真っ先に目に入るのは、全体的に“丸みを帯びたフォルム”です。これは戦隊ヒーローにおいて非常に珍しい特徴であり、従来のシャープで直線的な印象から一転、どこか柔らかくユーモラスな雰囲気を醸し出しています。
まず、スーツ自体のシルエットが角張っておらず、特に肩・腕・ヘルメットのラインが丸く滑らかにデザインされています。そのため、パッと見たときの印象が「強そう」よりも「可愛らしい」寄りになっており、一部視聴者には違和感を与える要因になっています。
さらに、各キャラクターの色使いにも注目する必要があります。基本の5人にはそれぞれ異なるカラーリングが設定されており、以下のような印象が見られます。
キャラクターごとのカラーデザインと印象
| キャラクター | メインカラー | 印象の傾向 |
|---|---|---|
| ブンレッド | 赤 | 目立つがクラシック感が強く、他キャラに比べて少し地味 |
| ブンブルー | 青 | 落ち着きがあるが、フォルムの丸さと色の暗さがミスマッチに感じられる |
| ブンピンク | ピンク | 柔らかさが強調され、子ども向けアニメのキャラに見えるという声もある |
| ブンブラック | 黒 | 本来クールな印象のはずが、デザインの丸さでギャップが生じている |
| ブンオレンジ | オレンジ | 派手さと親しみやすさが共存するが、キャラの個性としてはやや埋もれがち |
このように、丸いフォルムに対して「濃くて主張の強い色」が組み合わさっているため、視覚的なアンバランスさが一部視聴者の目に「チグハグ」「洗練されていない」と映ってしまう原因になっています。
従来の戦隊ヒーローでは、直線的なスーツにメタリックカラーや艶感のある質感が好まれてきました。しかしブンブンジャーでは、色味がフラットでポップなため、より“おもちゃ感”が前面に出ています。これは子どもにとっては覚えやすく、視覚的にも楽しい工夫ではありますが、大人の視聴者からは「安っぽい」「迫力がない」といった否定的な声が出てしまいやすいポイントです。
デザインの丸さや色使いは、ブンブンジャーが“子ども向け”という原点に立ち返ったとも言える意欲的なチャレンジです。しかし、歴代シリーズと比較したとき、そのギャップが視聴者の評価を大きく二極化させているのは明らかです。
2-2. 顔のマークは「タイヤ」?過剰なシンプルさへの疑問
ブンブンジャーのビジュアルにおけるもう一つの特徴は、各キャラクターのマスク部分、つまり“顔”に刻まれた独特なマークです。このマークは明らかに「タイヤ」をモチーフにしており、ブンブン=車というテーマをわかりやすく表現しています。
ですが、このタイヤマークのデザインが「シンプルすぎて手抜きに見える」「もう少し凝ってほしかった」といった評価を受けているのも事実です。特に以下のような意見が目立ちました。
SNSや口コミでよく見かける指摘
- 「顔の真ん中にタイヤ…まんま過ぎて笑った」
- 「ギミックがなさすぎて安っぽく感じる」
- 「子どもがすぐに描けるようにしてるのはわかるけど、大人には物足りない」
このように、タイヤマークの“あまりにもストレートな表現”が、ユーザーにとっては「物足りなさ」や「雑さ」のように映っているのです。
実際に他の戦隊シリーズと比較してみると、その差は一目瞭然です。
顔デザインの比較一覧
| シリーズ名 | マスクデザインの特徴 |
|---|---|
| ブンブンジャー | タイヤマークを顔の中心に配置。細かい装飾なし |
| ドンブラザーズ | サングラス風デザイン+デジタル模様が融合され、情報量が多い |
| ゼンカイジャー | マシン感満載のメカフェイス。複数のパーツが複雑に組み合わさっている |
| キラメイジャー | 宝石をイメージした多角形のデザインで、きらびやかさと独自性を両立 |
こうして比べると、ブンブンジャーの顔のデザインは「わかりやすさ重視」であることがはっきりします。しかしその分、視聴者に“新しさ”や“インパクト”を与える力は弱くなってしまっています。
また、タイヤモチーフが5人全員共通で配置されているため、個性の違いがマスクからは感じられにくいという声もあります。これもまた「似たような顔に見える」「識別しづらい」といった指摘につながっています。
もちろん、こうしたシンプルなデザインには「認知のしやすさ」や「キャラグッズ展開のしやすさ」といった大きなメリットもあります。とくに低年齢層の子どもがパッと見て「これがブンレッド!これがブンブルー!」と理解しやすい構造は、戦略として理にかなっています。
しかし、初見で「カッコよさ」や「斬新さ」を求める層にとっては、この“過剰に簡略化されたタイヤマーク”が、残念ながら「ダサい」と感じられる最大の要因になっていることは否定できません。今後の展開で、より個性が見える演出やアップグレードがなされるかどうかが注目されます。
2-3. ブンブン○○系ネーミングの統一感と限界
ブンブンジャーの大きな特徴のひとつが、「ブンブン○○」というネーミングの一貫性です。キャラクター名から乗り物名、さらには武器やロボに至るまで、あらゆる名称に“ブン”という単語が組み込まれています。これはシリーズ全体に統一感を持たせ、子どもたちの記憶に残りやすくするための狙いがあると考えられます。
たとえば、登場キャラの名前は以下の通りです。
キャラクター名一覧
- ブンレッド(井内悠陽)
- ブンブルー(葉山侑樹)
- ブンピンク(鈴木美羽)
- ブンブラック(齋藤璃佑)
- ブンオレンジ(相馬理)
このように、全員に「ブン」が頭につくことで、ブランドとしての統一性は確保されています。さらに乗り物やロボットにも同様のルールが適用されています。
メカ・ロボットのネーミング例
| メカ名 | 説明 |
|---|---|
| ブンブンスーパーカー | ブンレッドが操縦するスピード型マシン |
| ブンブントレーラー | ブンブルーが使う大型車両でパワー重視の設計 |
| ブンブンオフロード | ブンブラックが操縦するオフロード車 |
| ブンブンワゴン | ブンオレンジのサポートマシン |
確かにこれらのネーミングはわかりやすく、シリーズのテーマである“車”と“走る音”をしっかり表現しています。しかし一方で、大人の視聴者やシリーズファンからは「さすがに安直すぎる」「もうちょっと捻りが欲しい」という声も多く見られます。
指摘される「ブンブンネーミング」の限界
- すべて同じリズムなので、名前に個性を感じにくい
- 「ブンブンスーパーカー」など、やや冗長で語感が重たい印象
- 英語や横文字の混在がないため、世界観が単調に見える
特に“スーパーカー”“トレーラー”“ワゴン”といったネーミングは、子どもには伝わりやすいものの、大人にとっては直球すぎて面白みに欠けると感じられがちです。
さらに、「ブンレッド」「ブンブルー」といった名前は、過去の戦隊シリーズと比較しても非常にシンプルで、特に記号性が強いため、個々のキャラクター性や物語との関連性が見えにくいという課題もあります。
とはいえ、この「ブンブンネーミング」は狙いが明確です。どのキャラ、どのメカも一発で“ブンブンジャーの仲間”だと分かる設計になっており、子どもたちに覚えてもらいやすく、関連グッズもすぐに認識されやすいという大きなメリットがあります。
つまり、統一感のあるネーミングが「親しみやすさ」を生む反面、「深みのなさ」という限界にも直面しているのです。このバランスをどう受け取るかによって、評価が大きく分かれるポイントとなっています。
3. 「語尾にブン」はダサい?遊び心と違和感の境界線
ブンブンジャーの特徴の中でも、とくにSNS上でインパクトを残したのが「語尾にブン」です。これは公式Xの投稿や番組内のナレーション、一部キャラクターのセリフなどで使われており、明確に“狙っている”要素だと感じられます。
たとえば、公式が2024年3月10日に投稿したフレーズ「いかがだったブン?」は、その独特な語尾によって視聴者の注目を集めました。一部ユーザーはこれを見て、「子ども向けとしてはアリ」「おふざけが過ぎる」「まさかこれが本気なのか」と様々な意見を交わしていました。
語尾“ブン”に対するSNSでの反応(代表例)
- 「語尾ブンに笑った、これは新ジャンル」
- 「真剣なシーンでも“ブン”つけられると集中できない」
- 「語尾に“ブン”って…狙いすぎて逆にスベってる感」
では、この“語尾にブン”という演出は、なぜ賛否が分かれるのでしょうか?結論から言えば、それは「遊び心と違和感のバランス」が微妙なラインにあるためです。
語尾にブンが与える印象と評価軸
| 要素 | ポジティブな評価 | ネガティブな評価 |
|---|---|---|
| 遊び心 | 覚えやすい/親しみやすい/子どもウケ抜群 | 幼稚すぎる/ふざけて見える/シリアスさが薄れる |
| ユーモアの演出 | キャラに愛着が湧く/SNS映えする | 真面目なシーンが台無しになる場合がある |
| 独自性 | 他作品との差別化につながる | わざとらしくて寒いと感じる視聴者もいる |
とくに戦隊シリーズは「熱い展開」「ドラマ性」を重要視してきた伝統があるため、そこに「語尾ブン」が組み合わさると、一部ファンには「緊張感が削がれる」「ギャグ路線が強すぎる」と映ってしまうのです。
ただし、この“語尾ブン”は間違いなくキャッチーで、子どもたちが真似しやすいというメリットがあります。たとえば日常会話で「今日は楽しかったブン!」と真似する子どもたちが現れれば、それはすでに作品が文化として浸透し始めている証です。
また、過去にも「語尾キャラ」が受け入れられた作品は多数あります。ポケモンの「ピカチュウ」や、妖怪ウォッチの「ジバニャン」など、子どもたちの間では“語尾”が強烈な個性となることは珍しくありません。
そのため、“語尾ブン”は決して失敗ではなく、むしろ明確に子どもターゲットに向けた言語設計と言えます。問題は、これをどう物語の中で自然に取り入れていくか、そしてそれが子ども以外の視聴者にも“納得できる面白さ”として伝わるかどうかです。
「ダサい」と感じるか、「面白い」と感じるかは、完全に見る側の受け取り方次第です。制作者側がここまで“狙ってブン”を使っている以上、今後の展開でどのように昇華されるのかに注目が集まります。
3-1. キャラクターセリフと公式Xの文体に見る「ネタ感」
ブンブンジャーが「ダサい」と言われる理由のひとつに、公式X(旧Twitter)やキャラクターのセリフからにじみ出る“ネタ感”があります。この「ネタ感」とは、あえておふざけやギャグっぽさを強調するような表現を指しており、意図的にユーモアを仕込んでいることが見受けられます。
最初に話題となったのは、公式Xでの投稿文。「いかがだったブン?」という投稿は、戦隊ヒーローらしからぬ軽妙な語り口で、視聴者に強いインパクトを与えました。
公式Xの特徴的な投稿例
- 「次回もブンブンお楽しみにブン!」
- 「今日も爆上げしたブンか〜?」
- 「#バクアゲタイムズで感想聞かせてブン!」
これらの投稿を見ると、まるでマスコットキャラのような言葉づかいで語られており、硬派な特撮ファンからは「なぜこんな文体?」と戸惑いの声も上がりました。一方、親しみやすさや親バカ感を楽しむ層からは、「これはこれでアリ」「逆にクセになる」といった反応も見られています。
また、番組内のキャラクターたちも、ところどころで「〜ブン!」と語尾に付けたり、戦闘中に「爆上げだブン!」などのセリフを発したりと、ブンブンワールド全開の発言が随所に散りばめられています。こうしたセリフ回しは、従来の戦隊シリーズと比較してもかなり“おふざけ寄り”で、物語の緊張感をあえて和らげるような役割を果たしています。
“ネタ感”が出る要素一覧
| 要素 | 内容例・特徴 |
|---|---|
| 語尾表現 | キャラ・ナレーション・公式が「〜ブン」で語る |
| ネーミングのユルさ | 「ブンブンスーパーカー」「ブンピンク」など覚えやすくもダサ可愛い名前 |
| ハッシュタグや言い回し | 「#バクアゲ」「#ブンブンしようぜ」など、若干ふざけ気味なネットスラング感覚 |
| セリフのトーン | 熱血というよりは陽気/ノリが軽く、シリアスになりすぎない |
このように、作品全体に「ネタとしても楽しんでください」というメッセージが込められている印象を受けます。特にSNSと連動した戦略では、ただ真面目なだけでは拡散力に欠けるため、あえて笑われる要素を盛り込むことで「トレンドに乗る」「話題にしてもらう」ことを優先している可能性も高いです。
その結果、「なんか軽い」「ギャグ作品みたい」というイメージを持たれてしまい、ブンブンジャー=ダサいという構図が一部で成立しているのです。しかし裏を返せば、これは“笑われる覚悟”を持って作られている証拠でもあります。ネタ感が強すぎると感じるか、それを愛すべき個性と捉えるかは、視聴者の感性に委ねられています。
3-2. 他戦隊と比較して異質なのか?
ブンブンジャーが「異質だ」と感じられる大きな理由のひとつは、過去のスーパー戦隊シリーズとの比較にあります。戦隊モノは長い歴史を持ち、1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』から始まり、毎年新たなコンセプトと共に新シリーズが展開されてきました。その中でも、ブンブンジャーは明らかに“方向性が違う”という印象を持たれがちです。
たとえば、近年のシリーズをいくつか振り返ってみましょう。
近年のスーパー戦隊シリーズとブンブンジャーの比較
| シリーズ名 | 主なテーマ | 特徴的な要素 |
|---|---|---|
| キラメイジャー(2020) | 宝石・クリエイティブ | ビジュアルが煌びやかで、ヒーローが芸術家・医師など多彩な職業持ち |
| ゼンカイジャー(2021) | 歴代戦隊+ロボテーマ | ロボが主役級で、コミカルながら戦闘演出はしっかりしていた |
| ドンブラザーズ(2022) | 桃太郎ベースのファンタジー | 個性的なCGキャラと人間ドラマが混在した異色作 |
| キョウリュウジャー(2013) | 恐竜&音楽 | 王道な熱血展開とパワフルな戦闘、ロック調の演出が人気だった |
| ブンブンジャー(2024) | 車×ギャグ×爆上げ | 丸いフォルム、語尾ブン、軽めのセリフなど、あえて“ダサさ”を前面に出している |
この比較から分かるように、ブンブンジャーは他作品に比べてビジュアルやセリフ、ネーミングセンスまで「全体的にポップでおふざけ路線」が強くなっています。
たとえば、『ゼンカイジャー』もかなりの変化球でしたが、そこには明確な“メタ視点”や“歴代シリーズのオマージュ”という企画意図がありました。『ドンブラザーズ』も奇抜なキャラデザインながらも、物語は非常にシリアスで深いテーマを描いていました。
それに比べてブンブンジャーは、第一印象から“ノリと勢い”が重視されており、ギャグ要素が非常に前面に出ています。つまり、他シリーズが「真面目だけどちょっと変わってる」なら、ブンブンジャーは「最初からふざけてるように見える」ため、異質に映るのです。
ブンブンジャーが“異質”とされる理由まとめ
- 全体的にビジュアルやネーミングがライトでギャグ寄り
- 語尾やキャッチフレーズがユーモア重視でトーンが軽い
- メッセージ性よりも「ノリの良さ」を強調した作風
とはいえ、“異質”だからこそ目立つのも事実です。戦隊シリーズは時代ごとにアプローチを変えており、その中で「爆上げ」「ブンブン」など、明確に時流を意識したブンブンジャーの方向性は、新たなファン層を開拓するためのチャレンジとも言えます。
つまり、ブンブンジャーはただ変わった戦隊ではなく、「SNS時代にウケる戦隊」として、あえて異質な立ち位置を取っているのです。受け手の価値観によって“ダサさ”にも“先進性”にも見える。それが、今作の最大の魅力であり、賛否を呼ぶ理由なのです。
4. キャストがイケメンすぎる問題:「見た目」と「設定」のギャップがダサさを強調?
ブンブンジャーのキャスト陣は、そのビジュアル面において“戦隊シリーズ屈指のイケメン揃い”とも言えるほど華があります。各メンバーは舞台やモデル、ドラマ経験もある実力派・新鋭ぞろいで、そのスタイリッシュな容姿はSNSでも「レベル高すぎ」と注目されています。
しかし、その“イケメンっぷり”が、逆に「設定やデザインとのギャップを生んでいる」という見方も少なくありません。丸っこいスーツ、コミカルなネーミング、「語尾にブン」といったお茶目な演出が満載の中に、クールすぎるキャストを配置することで、「見た目とのギャップが笑える」「ビジュアルと設定がちぐはぐに見える」といった声がSNSでも多く見られています。
よくある視聴者のリアクション
- 「顔がイケメンすぎて“ブンブルー”って名前との落差がすごい」
- 「この見た目で“ブンブンスーパーカー”に乗ってるのウケる」
- 「顔面偏差値が高すぎるとダサい演出が際立って見える説ある」
このように、あまりにも整ったルックスと、わざとチープに設計された世界観との対比が、逆に“ダサさ”を強調してしまっているという現象が起きています。
ただし、このギャップは決してマイナスだけではありません。むしろ現代のコンテンツにおいては、そうした“ちぐはぐさ”がネタとして拡散されたり、「ギャップ萌え」として愛される要素になるケースも多いです。ブンブンジャーもその典型例で、イケメン俳優がポップな衣装で「ブン!」と叫ぶ姿に、視聴者はツッコミつつもハマっていくのです。
4-1. 各キャラのプロフィール紹介と魅力
それでは、ブンブンジャーの個性あふれるキャストたちを、それぞれ詳しく見ていきましょう。俳優としてのバックグラウンドや趣味・特技まで含めて知ることで、彼らの魅力と、作品内での役割がより深く理解できます。
ブンレッド(演:井内悠陽)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誕生日 | 2004年7月12日 |
| 出身地 | 京都府 |
| 趣味・特技 | 読書、ダンス、作詞・作曲、アクション、ギター |
| 魅力ポイント | 若手ながら演技に安定感があり、アクションもこなせる多才型。リーダーらしい安定感と表情の豊かさが武器です。 |
ブンブルー(演:葉山侑樹)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誕生日 | 2001年10月27日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 趣味・特技 | 食べ歩き、サウナ、ピザ作り、バスケ |
| 魅力ポイント | 落ち着いた雰囲気と高身長が映えるクールキャラ。アクションシーンでのキレと、笑顔のギャップが女性ファンに人気です。 |
ブンピンク(演:鈴木美羽)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誕生日 | 2000年4月14日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 趣味・特技 | フィルムカメラ、ラーメン屋巡り、サウナ、書道八段 |
| 魅力ポイント | モデル出身らしい華やかさと繊細な表現力を兼ね備えた演技派。正統派ヒロインながらも個性の強い存在感があります。 |
ブンブラック(演:齋藤璃佑)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誕生日 | 2004年6月16日 |
| 出身地 | 秋田県 |
| 趣味・特技 | 筋トレ、漫画、スキー、イラスト、バスケ |
| 魅力ポイント | 男らしさとお茶目さを両立した“陽キャ”系。チームの盛り上げ役でありながら、熱いシーンでは真剣な眼差しで魅せてくれます。 |
ブンオレンジ(演:相馬理)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誕生日 | 1996年10月23日 |
| 出身地 | 静岡県 |
| 趣味・特技 | サッカー、ランニング |
| 魅力ポイント | 最年長の包容力と落ち着きでチームを支える兄貴分。笑顔とアクションのギャップが魅力で、父親世代の視聴者からも好評です。 |
これらのキャストは、それぞれが独自の個性とスキルを持っており、見た目だけでなく、役柄としての深みも十分に持っています。だからこそ、ポップな世界観とのギャップが強烈に際立ち、「ブンブンジャー=ダサいのにかっこいい」という不思議なバランスを成立させているのです。
戦隊シリーズでは毎年、新たなスターが誕生していますが、今年のブンブンジャーもその例に漏れず、今後の活躍が大いに期待できる布陣です。彼らの魅力が、今後どのように“ダサかわいい”ブンブンワールドを深めていくのか、注目していきましょう。
4-2. なぜイケメン起用でも「ダサい」と言われるのか?
一見すると、ブンブンジャーは「若手イケメン俳優を揃えて、華やかな戦隊モノに仕上げた作品」に思えるかもしれません。事実、5人のキャストはルックスも実績も申し分なく、モデル経験者や舞台俳優として活躍しているメンバーも含まれています。それにもかかわらず、「なんかダサい」「イケメンなのに笑っちゃう」と言われてしまうのはなぜなのでしょうか。
その理由は、“イケメンと設定のギャップ”にあります。
ギャップがもたらす「違和感」
スーツの丸っこいフォルム、語尾に「ブン」、ロボットの名称が「ブンブンスーパーカー」など、作中に散りばめられた演出が非常にポップかつユニークであるため、視聴者は無意識に「コミカルな作風」と受け取ります。
そこに、キリッとした顔立ちのイケメンが真面目に「爆上げだブン!」などと叫ぶわけです。視覚と聴覚から入ってくる情報がミスマッチで、良くも悪くも“笑い”を誘ってしまうのです。
視覚と演出のギャップ例
| 要素 | 見た目(視覚情報) | 演出(セリフ・設定) |
|---|---|---|
| 俳優陣のルックス | クールで洗練されたイケメン揃い | 語尾に「ブン」、ポップな言い回し |
| スーツデザイン | 丸みのある可愛らしいフォルム | 戦闘時に“爆上げ”などの軽快なセリフ |
| メカ・ロボのビジュアル | カラフルで子ども向けな印象 | ネーミングが「ブンブン○○」で徹底統一 |
このような“真顔でふざけたセリフを言う”演出は、意図的なギャップ演出とも考えられます。コント番組で俳優が真面目な顔でボケる場面が面白いのと同じように、狙って「おかしさ」を作っている可能性は高いです。
イケメンゆえの「目立ち方」
もうひとつの理由は、イケメンだからこそ“浮いて見える”という現象です。戦隊シリーズは、ストーリーや演出がメインで、役者の顔が過剰に目立つことはあまりありません。しかしブンブンジャーは、ビジュアル重視のキャスト構成とポップな世界観がミックスされており、「顔の良さ」が逆にアンバランスさを際立たせてしまっています。
視聴者からは、こんな声も多く聞かれます。
- 「かっこいいのに、なんで“ブンオレンジ”?名前とのギャップがすごい」
- 「真面目な顔で“ブンブンワゴン出動!”って言ってるの、ツボすぎる」
- 「むしろこのアンバランスさがクセになる」
結論として、イケメンであること自体はむしろプラス材料です。ただ、作品の持つ独特の世界観や演出があまりにもキャッチーすぎて、俳優の“かっこよさ”とのギャップが生じ、その違和感が“ダサさ”として捉えられてしまうのです。
5. 過去の戦隊シリーズと比べて本当にダサい?【比較レビュー】
ブンブンジャーは「過去イチでダサい」と言われることもありますが、実際に歴代のスーパー戦隊シリーズと比較するとどうなのでしょうか?このセクションでは、過去のユニークな戦隊と比較しながら、ブンブンジャーが本当に“突出してダサい”のかを検証します。
過去にも「ダサい」と言われた戦隊は存在する
まずは「当時はダサいと言われたが、今は愛されている戦隊」から見ていきます。
過去のユニーク路線戦隊と評価の変遷
| 戦隊名 | 放送年 | 主な特徴 | 当時の評価 | 現在の評価 |
|---|---|---|---|---|
| 激走戦隊カーレンジャー | 1996年 | 車ギャグ全開、ゆるいノリ | ギャグすぎて異端視 | ネタ系戦隊の元祖として人気復活 |
| 侍戦隊シンケンジャー | 2009年 | 和風・漢字がモチーフ | 地味で堅苦しいとの声も | ストーリー評価が高く再評価 |
| 獣電戦隊キョウリュウジャー | 2013年 | ダンスあり、明るいキャラ設計 | 明るすぎて子ども向けすぎる | ノリの良さと音楽性で好評 |
| 機界戦隊ゼンカイジャー | 2021年 | ロボ×人間のコンビ、斬新すぎる構成 | 奇抜すぎると賛否両論 | メタ演出の面白さで評価上昇 |
これらを踏まえると、ブンブンジャーも“奇抜枠”の系譜をしっかり継いでいると言えます。つまり、いまは笑われている部分が、将来的には“名物”として語られる可能性があるということです。
デザイン・設定面での比較
では、ブンブンジャーの「ダサさ」はどこまで本当なのか。デザイン・設定・演出の3つの面から、過去シリーズと並べて比較してみましょう。
比較ポイント一覧
| 比較項目 | ブンブンジャー | 過去の戦隊(例:ゼンカイジャー、カーレンジャーなど) |
|---|---|---|
| スーツデザイン | 丸み重視・ポップ調 | メカ系、和風、動物モチーフなどシリーズごとに多様化 |
| ロボ・メカ | 全車両名に「ブンブン」が付く、可愛いデザイン | カーレンジャーも車モチーフだが、そこまでネタには振り切っていない |
| セリフ・演出 | 「語尾ブン」や「爆上げ」などユーモラスな言葉遊び | キメ台詞やBGMが王道系だったシリーズが多い |
| ネーミング | キャラ名も「ブン○○」で統一 | 多少ひねりのある名前(例:シンケンレッド、ドンモモタロウなど) |
こうして比較すると、ブンブンジャーは「徹底してわかりやすさと親しみやすさ」に振り切った戦隊であることがわかります。それが「ダサさ」として見られてしまう反面、実は過去シリーズが取り入れていた要素をさらに大胆に、そして極端に表現しているとも言えるのです。
“ダサい”はむしろ武器?
戦隊シリーズは、長年「カッコよさ」を前面に押し出してきました。しかし近年は、“ふざけた設定”や“振り切った演出”が逆にウケる時代です。YouTubeでの切り抜き、SNSでのネタ投稿、TikTokでのコスプレパロディなど、作品外での広がりを意識した設計が主流になりつつあります。
ブンブンジャーもその潮流の中にいる戦隊です。見た目やノリの軽さで「ダサい」と言われながらも、話題性という点では圧倒的に強く、マーケティング的にも成功している部分があります。
つまり、過去と比べて“ダサさの意味”そのものが変化しているのです。昔ならマイナスだった表現が、いまは「クセになる魅力」としてポジティブに転化されているケースも少なくありません。
結論:本当にダサいのか? → 今の時代に合った“ネオ・ダサカッコイイ”戦隊
「ダサいから見ない」ではなく、「ダサいから気になる」「笑えるから見ちゃう」——そうした“時代にフィットした作品”であることが、ブンブンジャー最大の特徴です。
5-1. 『カーレンジャー』『ゴーオンジャー』などとの比較
ブンブンジャーを語るうえで避けて通れないのが、過去の“車モチーフ”戦隊との比較です。特に『激走戦隊カーレンジャー』(1996年)と『炎神戦隊ゴーオンジャー』(2008年)は、モチーフや作風の面でブンブンジャーと共通点が多く、比較対象として最も適しています。
では、それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
『激走戦隊カーレンジャー』との比較
カーレンジャーの特徴
- 放送当時は“ギャグ戦隊”として異端扱い
- 敵も味方も徹底的におふざけ路線
- ダサい演出やネーミングが話題に
- 放送当初の評価は低かったが、後年“カルト的人気”を獲得
ブンブンジャーとの共通点
| 比較項目 | カーレンジャー | ブンブンジャー |
|---|---|---|
| コンセプト | 車+ギャグ戦隊 | 車+爆上げ+ギャグ要素 |
| 名前の印象 | レッドレーサー、グリーンレーサーなど直球ネーミング | ブンレッド、ブンブルーなどシンプルネーミング |
| 演出の方向性 | 徹底したネタ路線 | ネタ感を匂わせつつも現代風に昇華 |
| 当時の評価 | 「ふざけすぎ」と言われ一部で酷評されていた | 「ダサすぎ」とSNSで賛否が分かれる |
| 現在の評価 | ネタ枠として再評価、「名作」との声も多い | 現在進行形で評価が揺れている段階 |
カーレンジャーは“時代が追いついた戦隊”の代表例とも言われています。当時「ダサい」と酷評された要素が、令和の視点で見ればむしろ「先を行っていた」ユーモアとして評価されるようになりました。ブンブンジャーにも、そのポテンシャルがあることは間違いありません。
『炎神戦隊ゴーオンジャー』との比較
ゴーオンジャーの特徴
- 車×動物を組み合わせたロボ構成
- 登場マシンが自我を持ち、会話するというユニークな設定
- ギャグ要素を取り入れつつも、熱血・友情・正義の三拍子を忘れないバランス型
- 主題歌やBGMも派手で記憶に残りやすく、子ども人気が非常に高かった
ブンブンジャーとの違い
| 比較項目 | ゴーオンジャー | ブンブンジャー |
|---|---|---|
| 車の扱い方 | メカに人格があり、感情や会話でドラマを演出 | 車そのものに人格はなく、記号的存在(名称に“ブンブン”付与) |
| キャラデザイン | スーツのメリハリが強く、顔もシャープ | 丸みを帯びたシルエット、顔がシンプル |
| ノリ・テンション | 高めだがストーリーに説得力がある | 軽くポップな演出が全面に出ており“ネタ枠”に近い |
| ネーミングのセンス | 「スピードル」「バスオン」などユニークだが覚えやすい | 「ブンブンスーパーカー」など直球すぎて逆に笑える |
ゴーオンジャーは“子ども受けしつつ、大人も納得できるバランス感”が魅力でした。それに対して、ブンブンジャーはその“バランス”をあえて崩して、振り切ったキャッチーさに舵を切っています。結果として、深みよりも“目立つこと”を優先している印象が強く、それが「ダサさ」と受け取られている要因のひとつです。
5-2. ダサさは「狙い」か「事故」か?
ここまで見てきた通り、ブンブンジャーに散りばめられた「ダサい」と言われる要素は枚挙にいとまがありません。では、これらの“ダサさ”は偶然の産物なのか?それとも、制作側が意図して仕掛けたものなのか?結論から言えば、明らかに「狙ったダサさ」であると断言できます。
「狙い」の根拠1:徹底されたブランディング戦略
まず、すべての名称に「ブン」を付けるという統一感は、偶然ではなく意図されたブランド戦略です。キャラクター名、メカ、技、公式SNSの言葉遣いまで、全方向で「ブンブンワールド」が構築されています。
また、公式Xの投稿でも、あえて「語尾にブン」「爆上げ」という言葉を繰り返しており、ふざけているように見えて、その言語設計には一貫性があります。これが仮に“無意識”であれば、逆に不自然です。
「狙い」の根拠2:子ども向け市場に対するアプローチ
現代の戦隊シリーズは、ターゲットである子どもたちにとって「わかりやすさ」「真似しやすさ」「リズムの良さ」が非常に重要です。「ブンブン」「爆上げ」「いかがだったブン?」といったワードは、語感がよく、一度聞けば耳に残るものばかりです。
つまり、これはダサいというよりあえて幼児向けに“覚えさせやすい”工夫として設計されているということです。
「狙い」の根拠3:SNS映えと話題性
ブンブンジャーは放送初日からSNSで話題になり、「トレンド入り」も果たしました。これは、ある意味で“炎上上等”とも取れるプロモーションです。賛否が分かれるデザイン、ネーミング、演出は、拡散される材料としては最高です。
現代のメディア消費では、完璧よりも「ネタにできる」ことが重要視される傾向があります。ブンブンジャーは、まさにその文脈を踏まえて制作された作品です。
では“事故”の要素はないのか?
もちろん、視聴者の想定を超える“滑り方”をしてしまったシーンやセリフはあるかもしれません。しかし、それはあくまで「実行段階でのブレ」であって、企画や構成自体は非常に緻密に作られています。
「狙ってダサくしたけど、予想以上にツッコミが殺到した」という現象はあり得ます。しかし、ブンブンジャーが根本的に“ノープランのごちゃ混ぜ”作品であるとは言えません。むしろ、その徹底されたテーマ設計と演出手法は、狙って仕掛けてきている証拠だと言えるでしょう。
結論:ブンブンジャーのダサさは“戦略的エンタメ”
ブンブンジャーは、ただの戦隊作品ではありません。今どきの子ども向け作品として「ネタ」「拡散」「ギャップ」「クセになる」要素を緻密に練り上げた戦略型コンテンツです。
その中で演出された“ダサさ”は、実はもっとも計算された要素のひとつ。大人が思わず「ダサい」とツッコむ構造自体が、視聴者参加型のエンタメ体験として設計されているのです。
だからこそ、今後ブンブンジャーは「笑われる」だけでなく、「笑って応援される」存在になっていく可能性があります。ダサさを恐れず、ダサさを武器にした、新しいヒーロー像がここにあるのです。
6. 「ダサい=話題性」の法則?バズ狙いの可能性を考察
ブンブンジャーを取り巻く「ダサい」という評価が、じつは“作品の強みに変わっている”という現象に気づいている人も増えてきています。今やエンタメ業界では、「本気でカッコいい作品」だけでなく、「一周回って笑われる作品」が話題になる時代です。ブンブンジャーのダサさも、単なるマイナスポイントではなく、“バズるための仕掛け”として設計されている可能性が非常に高いです。
このセクションでは、「なぜダサいものが広がるのか?」という視点から、SNS時代のマーケティング戦略と絡めてブンブンジャーを読み解いていきます。
なぜ「ダサい」がバズるのか?
SNSでは、シンプルに「すごい」「かっこいい」と言われるよりも、「なんだこれ?(笑)」「これはアカンやろ」といったネタ系の投稿の方が反応率が高く、拡散されやすい傾向があります。
なぜなら、ユーザーは驚きや違和感を覚えるものに対して“ツッコミを入れたくなる”からです。これは「ツッコミ欲求」とも呼ばれ、SNSでのコンテンツ拡散において非常に強力な要素です。
ブンブンジャーに関しては、以下のようなツッコミどころが満載です。
ブンブンジャーの“ツッコミどころ”
- 名前が「ブンレッド」「ブンピンク」など単純すぎる
- ロボの名前が「ブンブンワゴン」などで統一されている
- 公式Xでの「いかがだったブン?」という語尾
- キャラが真顔で「爆上げ!」と叫ぶシーン
- 顔に描かれたシンプルな“タイヤ風”マーク
これらはすべて、視聴者が「ネタにしやすい」要素であり、投稿やリプライで使いたくなるパーツばかりです。
反応を呼びやすいSNS投稿例(実際の傾向)
- 「このネーミング攻めすぎだろwww」
- 「語尾ブンは反則すぎる」
- 「イケメンに爆上げとか言わせるのやめてw」
- 「子どもは喜んでるけど親が一番ハマってる説」
つまり、ブンブンジャーはネタとして話題になりやすい構造が、番組全体に組み込まれているのです。
6-1. SNSでの拡散性とマーケティング戦略
ここでは、ブンブンジャーが実際にどのようにSNSで拡散され、そこにどんなマーケティング戦略が隠されているのかを分析していきます。
① トレンドワード化を狙った語彙設計
「爆上げ」「ブンブン」「いかがだったブン?」といったワードは、いずれも日常会話に混ぜやすく、真似しやすい言葉です。SNSに投稿する際も、ハッシュタグやツイート文にそのまま使えるため、自然と拡散されやすくなります。
たとえば、公式が積極的に使用しているハッシュタグ例は以下の通りです。
公式によるハッシュタグ戦略
| ハッシュタグ | 目的 |
|---|---|
| #爆上戦隊ブンブンジャー | 認知拡大・シリーズ全体の統一タグ |
| #バクアゲタイムズ | SNS投稿誘導・反応の見える化 |
| #ブンブンしようぜ | キャラ性の拡張・ネタツイート促進 |
このように、ユーザーが自然に使いたくなる短くてユニークなタグを用意することで、「シェアされる前提」での設計がなされているのです。
② 公式SNSの“人間味”ある運用スタイル
公式Xの投稿文には、あえて“砕けた”文体や“語尾ブン”などを用いて、ユーザーとの距離を縮めるスタイルが採用されています。これは、従来のヒーロー系コンテンツのように堅苦しくならず、あえて「ツッコミ待ち」に振り切っている点が特徴です。
その結果、視聴者はツイートにツッコミを入れたり、ミーム化したりすることで、作品への関与度が高まります。これは「共創型マーケティング」とも言われ、ユーザー自身が作品の一部として参加することを促進します。
③ 「イケメン×ポップデザイン」のギャップを演出
ビジュアル重視の俳優を起用しながらも、衣装や演出をあえてポップで幼稚にすることで、“ギャップ萌え”や“シュールさ”が際立ちます。これはSNSで映えるコンテンツとして、非常に計算された作りです。
SNS投稿におけるギャップの例
- 「この顔面で“ブンブンスーパーカー”って言わせる制作陣、天才か?」
- 「マスクのデザインが雑すぎて逆にクセになる」
- 「顔が良すぎるから語尾ブンが浮きまくってるのに、それがまた良い」
こうした投稿は、X(旧Twitter)、TikTok、Instagramなどで共感を呼び、連鎖的に拡散されていく仕組みを持っています。
結論:ブンブンジャーの“ダサさ”は、SNS時代の新しいヒーローマーケティング
「ダサい」と言われるのは、ネガティブな評価とは限りません。むしろブンブンジャーの場合、それが最大の拡散エンジンとなっています。SNSでの“話題化”を徹底的に狙ったブランディング設計、誰もがネタにしやすいギャップ演出、そしてハッシュタグや言葉選びに至るまで、すべてが一貫して「拡散されること」を目的とした作りになっているのです。
今の時代、「笑われる」ことは「愛される」ことへの第一歩です。ブンブンジャーはその現代的価値観を巧みに取り入れた、新時代型の“話題先行型ヒーロー”と言えるでしょう。
6-2. ダサさがクセになる理由とは
「ブンブンジャーはダサい」と言われながらも、気がつけば毎週見てしまう…そんな視聴者が増えています。実際、SNSでは「最初は笑ってたのに、今はもう日曜の楽しみになってる」「ダサいのが逆に心地よくなってきた」といった投稿が多数見られます。
ではなぜ、ダサさが“クセになる”のでしょうか?その理由は、大きく分けて以下の3つに集約できます。
① 記憶に残るインパクトの強さ
「ブンレッド」「ブンブンワゴン」「爆上げだブン!」——どれも一度聞いたら忘れられないワードです。語感が面白く、ネーミングがストレートすぎるがゆえに、記憶に焼き付いてしまいます。これは、脳が“普通じゃないもの”に強く反応する特性を巧みに突いています。
特に子どもたちは、「覚えやすい・真似しやすい・声に出したくなる」ワードを自然に好みます。語尾に「ブン」がつくだけで、それがユーモラスな遊び言葉に変わるので、日常生活でも使いたくなってしまうのです。
② 親しみやすさと「ツッコミどころ」の多さ
ブンブンジャーのキャラや設定は、あえて「完璧ではない作り」にすることで、視聴者が気軽にツッコミを入れられる余地を作っています。この“ツッコミどころ”が、むしろ愛着につながっているのです。
たとえば以下のようなリアクションがSNSでよく見られます。
- 「また語尾ブンかよ!でも好き」
- 「マスクのタイヤ、やっぱり気になるw」
- 「ブンブン○○ってネーミング、毎週増えていくの楽しみになってきた」
こうした小さな違和感が「クセになるリズム」となって習慣化されていきます。つまり、“ダサいけどツッコミどころがあって楽しい”というバランスが、視聴者の心を掴んでいるのです。
③ ギャップ萌えと「ツンデレ構造」
イケメン俳優が丸っこいスーツを着て「爆上げだブン!」と叫ぶ。このギャップがシュールで笑える一方、真剣な演技やアクションシーンで見せる表情にはグッとくる。このように、視聴者は“ダサさの中にあるカッコよさ”を見つけ出すプロセスを楽しんでいるのです。
これはいわば、作品自体が“ツンデレ”構造になっているとも言えます。
- 普段はちょっとふざけてる(=ダサい)
- でも本気になるとめっちゃかっこいい(=キュンとくる)
この振り幅が大きいことで、感情のジェットコースターに乗せられてしまい、気づけば虜になっている——それが、ブンブンジャーが「クセになる」と言われる最大の理由です。
7. それでもハマる!ブンブンジャーの本当の魅力
“ダサい”と言われながらも、ブンブンジャーには確かに“ハマる理由”があります。笑いながらツッコんでいたつもりが、いつの間にかストーリーに引き込まれ、キャラに感情移入してしまう。そんな魅力が、作品のあちこちに散りばめられています。
では、ブンブンジャーの「本当の魅力」とは何か?見た目やノリの裏側に隠された、本質的な面白さを3つの視点から掘り下げてみましょう。
① 作品全体に込められた“徹底したエンタメ精神”
ブンブンジャーは、第一話から「振り切ってる」印象を強く持たせます。ネーミング、デザイン、セリフ回し、音楽、どれをとっても一貫して明るく楽しく、テンポの良いエンタメを届けるという意志が感じられます。
特に、
- 「爆上げ」という時代に合ったワード選び
- 子どもでも口にしやすいセリフや効果音
- 毎週新しいブンブン○○が登場するワクワク感
こうした演出が、日曜の朝にぴったりな“元気をくれる時間”を生み出してくれます。
② 戦隊ものの「王道」をしっかり押さえている
ブンブンジャーは奇抜に見えて、実は戦隊シリーズの王道要素も丁寧に組み込まれています。
- 毎回のピンチ→連携→勝利の流れ
- チーム内の信頼関係と成長描写
- 合体ロボの登場と必殺技の演出
こうしたフォーマットは、長年の戦隊ファンにとっても安心感があり、“型があるからこそ遊びが映える”という絶妙なバランスを保っています。
③ キャストの魅力と演技力の高さ
イケメン俳優が揃っているだけでなく、キャストたちの表現力や個性が、作品の世界観を引き立てています。とくに、ふざけたセリフでも真顔で言い切る“振り切った演技”にはプロ根性を感じますし、アクションや感情シーンの熱量も本物です。
また、それぞれのキャラクターがしっかりと個性を持っており、視聴を重ねるごとに「推し」ができる構成になっています。
結論:「ダサい」のその先にある、新しい面白さ
ブンブンジャーは、“完璧にカッコいい”を目指した作品ではありません。むしろ「ちょっと笑える」「ツッコミたくなる」「クセになる」ことを前提としながら、確かな王道と熱量を土台に、全力でエンタメを届けている作品です。
ダサさの中にある愛嬌、ポップな見た目の裏にある本気の演技、そして毎週の放送で感じる「今日も元気をもらったブン!」という気持ち。
それこそが、ブンブンジャーの“本当の魅力”です。ダサいけど、つい見たくなる。笑えるけど、心が熱くなる。そんなブンブンジャーを、これからも見逃せません。
7-1. 戦闘シーンの迫力とストーリー性
一見すると“ポップでネタっぽい”印象の強いブンブンジャーですが、実際の戦闘シーンでは驚くほど本格的なアクションが展開されており、視聴者を唸らせています。特に初回放送から数話を経るごとに、「あれ?想像以上にちゃんと戦ってる」「スーツの見た目に反してめっちゃカッコいい」といった声がSNSでも増えています。
本気のアクションで魅せる、ギャップの快感
ブンブンジャーは車をモチーフにしているだけあって、スピード感あふれる動きが多く採用されています。たとえば、ブンレッドはヒーローらしい直線的な突進攻撃を得意とし、ブンブルーはクールな間合いでのコンビネーションが光ります。
各キャラの戦闘スタイルにも個性があり、バラエティ豊かなアクションに仕上がっている点は高く評価できます。
戦闘シーンの注目ポイント
| キャラ名 | 戦闘スタイルの特徴 |
|---|---|
| ブンレッド | 突撃型。スピードと直進パワーで一気に切り込む |
| ブンブルー | バランス型。距離を取りながら冷静に立ち回る |
| ブンブラック | パワー型。豪快な一撃で敵を吹き飛ばす |
| ブンピンク | サポート型。トリッキーな動きで味方を援護 |
| ブンオレンジ | 機動型。身軽な動きで翻弄しつつ、スピード戦を制する |
スーツの丸みや色使いで“カッコよくない”と思いがちな視聴者が多い中、実際のバトルは本格的かつスピーディで、視覚的な満足感が非常に高いです。
また、カメラワークやエフェクトも最新技術が投入されており、演出面でのクオリティは歴代シリーズの中でもかなり上位レベルにあります。特に爆破シーンや武器使用時のCG合成などは、意外にも(失礼ながら)高精度で、子どもはもちろん大人が見てもテンションが上がるクオリティです。
ストーリー面でも実は“熱い”
もうひとつ見逃せないのが、ブンブンジャーのストーリー性です。序盤はノリ重視で始まりますが、回を重ねるごとに、チームの結束・成長・葛藤といった人間ドラマがしっかりと描かれていきます。
たとえば、リーダーであるブンレッドが仲間の迷いをどう受け止め、引っ張っていくのか。チームメンバーの背景にある過去や、敵との因縁がどう物語に絡んでくるのか。これらが明かされていくことで、視聴者はどんどん感情移入していきます。
特に、
- 仲間をかばって負傷するシーン
- 決意を胸に変身する場面
- 敵キャラの背景が判明して揺れる心情
といった“熱い展開”が定期的に挟まれる構成は、戦隊モノの醍醐味そのものです。
見た目や言葉の“ふざけ感”の裏で、こうした真剣なドラマパートを丁寧に仕込んでくる脚本は、まさに「王道の中の異端」。ネタ要素と感動要素が共存することで、視聴後に「今日のブンブン、意外と泣けた」なんて投稿がされるわけです。
結論:ふざけて見せて、しっかり燃えさせる設計
ブンブンジャーの戦闘とストーリーは、見た目に反して真剣そのもの。むしろ「軽く見せておいて、しっかりアツくする」という構成は非常に戦略的です。ネタを楽しみに来た視聴者を、そのまま王道ストーリーに引きずり込む“ギャップ演出”が、ブンブンジャーの巧みさと言えるでしょう。
7-2. 子どもたちの人気はどうなっている?
戦隊シリーズの最大のターゲットは、やはり未就学〜小学校低学年の子どもたちです。ブンブンジャーの「ダサかわいさ」「真似しやすさ」「テンポの良さ」は、まさにこの世代を強く意識した設計になっており、実際に子どもたちの間ではすでに高い人気を獲得しつつあります。
テレビだけじゃない!幼児向けYouTubeやイベントも好評
特に目立つのは、YouTubeのキッズ向け公式チャンネルでの再生回数の多さや、親子イベントでの登場時の盛り上がりです。変身バンク、主題歌、キャラ紹介など、短尺の動画でも子どもが集中しやすいようテンポよく構成されており、リピート視聴される傾向にあります。
また、「変身ポーズ」や「語尾ブン」など、すぐに真似できる要素が満載なため、幼稚園や保育園でのごっこ遊びにもしっかり浸透しているとの報告もあります。
グッズ展開の反響も上々
ブンブンジャーは、玩具の売上という面でも注目されています。
人気のグッズ例(2025年上半期)
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| ブンブンチェンジャー | 変身アイテム。軽量で持ちやすく、光と音で演出が派手 |
| ブンブンスーパーカー | 主人公専用マシン。車としても遊べて合体可能。 |
| ブンブン合体ロボ | ロボ好きな子どもに大人気。パーツごとの組み替えでバリエーション豊富 |
| ブンブンおしゃべりぬいぐるみ | 「爆上げだブン!」としゃべるマスコット。寝る前のお供にもなる人気アイテム |
これらの商品は、誕生日プレゼントやクリスマスなどの定番になりつつあり、子ども番組としての影響力はしっかりと発揮されています。
子どもと親の“二段構えターゲティング”
ブンブンジャーは子ども向けでありながら、大人(とくに親世代)もSNSで巻き込む仕組みになっています。親子で一緒に見られる内容にしておくことで、「子どもは戦闘や変身を楽しみ、親はギャップやネタを楽しむ」という構図が成立しています。
これにより、
- 子ども → 遊ぶ・真似する・好きになる
- 親 → SNSでネタにする・グッズを買う・思い出になる
という二段構えのファン層獲得に成功しているのです。
結論:子どもにウケる設計は、しっかり機能している
戦隊モノにとって最も大切なのは「子どもが夢中になれるかどうか」です。その点でブンブンジャーは、「見た目の分かりやすさ」「語感の面白さ」「真似したくなるアクション」を完備しており、まさに現代のキッズ市場を理解した作品になっています。
大人から見れば“ダサい”と映る部分こそが、子どもたちにとっては“楽しい”の原点。その絶妙なズレが、作品としての魅力とバズりやすさを両立させているのです。ブンブンジャーは、今日も「ブン!」と叫びながら、子どもたちの心をがっちりつかんでいます。

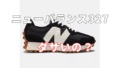
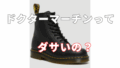
コメント